2006年3月にアートミーツケア学会が生まれて、まもなく20年になります。その目的として、会則には「人間の生の恢復を支えるアートやテクノロジーの役割を研究し、理論と実践の往還をすすめる。そして新しい知と新しい美の地平をひらき、人の生きやすい社会、文化をつくることを目的とする」とあります。
ここに書かれていることの意味は、およそ20年前にこの学会が立ち上がった時とは、大きく変わってきています。地域や社会と関わるアート活動は大幅に増えていますが、アートの道具化や商業化が進み、ハラスメントや労働の問題など、ケアとはほど遠いようなアートの現場に関する議論も行われるようになってきました。テクノロジーは文明を大きく進歩に導き、新たなコミュニケーションを創造していますが、その一方で社会全体がテクノロジーに支配され、翻弄される状況も続いています。
新しい知、新しい美の地平を、ともに想像すること。人の生きやすい社会を、そして文化を、これまでもこれからも、手足を動かしながら、考えて、生み出して、振り返って、また一歩を踏み出していくこと。アートミーツケア学会は、そのための研究の場です。ここで言う研究とは、研究者や大学の先生が行うものだけではありません。日々の生活や活動で感じることを深め、言葉にし、対話し、表現していくことから始まる、すべての人にとっての営みです。
会員による互選で理事を選ぶようになった2023年度に、当時の共同代表(ほんまなほ・森合音・長津結一郎)が中心となって立てた目標があります。
・アートとケアそれぞれの中心というよりは、そのふたつの周辺においてまじわるものの価値を社会へ発信する
・アートとケアを、マイノリティの視点などの、いくつもの角度からとらえなおす
・境界や分断を超えていく創造性に着目する
・理念を実践で語り合う
・あそびを通して参加する
今期(2025-2026年度)も基本的にはこの方向を継承しつつ、会員のみなさん一人ひとりの活動が少しずつ共有されたり、お互いにコミュニケーションするような時間をたいせつにした運営を心がけていきたいと思っています。
分断がますます著しいこの社会において、人が人として生きていけるための文化のあり方を考えていく場は、今もなお求められています。設立当初から大切にされてきた「学会らしくない学会」というあり方を常に意識しながら、多くの人たちとともに一歩ずつ進んでいきたいと思います。
2025年8月31日
アートミーツケア学会
代表 長津結一郎
副代表 岩田祐佳梨・柊伸江
————
◆代表・長津結一郎
2023年度から継続してアートミーツケア学会の運営に関わらせていただいておりますが、この度代表に就任することになりました。これまで学会の牽引や運営にご尽力いただいた方々を思うと、その重みを日々感じています。ただし、代表という肩書きではありますが、会員のみなさんの思いをもとに、バランスを取りながら運営を行っていきたいと考えています。この学会やその役割を、潜在的に求めている人たちは、学会の内外にたくさんいらっしゃると考えています。年に1度の大会やジャーナルはもちろん、それ以外の取り組みも含めて、副代表のお二人や理事のみなさん、事務局のみなさんと協力しながら運営することで、一緒に考えるための場をひらき、議論し、ネットワークを広げていくような2年間にできればと思います。

◆副代表・岩田祐佳梨
初めてアートミーツケア学会に参加したのは、2010年のせんだいメディアテークでの大会。実践も知識も中途半端で悶々としていた学生でした。そこでは、アートとケアの交わるところにある掴みきれない魅力と葛藤を言葉にしたい、越境していく難しさや面白さを他の人と共有したい、そういう思いを持つ人たちが集まっていて、実践と研究を行き来する楽しさを教えてくれたように思います。そして、15年後の今、代表の長津さん、副代表の柊さん、理事の皆さんと学会の運営に携わることになりました。知性と創造性と優しさにあふれるこのコミュニティが必要とする人に届き、社会に発信していけるよう、皆さんと共に学会を作っていけたらと思います。
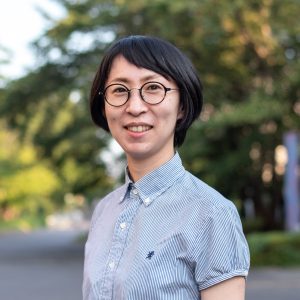
◆副代表・柊伸江
研究者でもなく、専門家でもない私が、この度、アートミーツケア学会の副代表を担わせていただくことになりました。これでおわかりいただけると思いますが、このアートミーツケア学会はなんの垣根もなく、会員同士がフラットに交流しあえる場です。長い人生の中で、学べる時間、学べる機会は限られていると感じています。だからこそ、他分野、多世代、他職種の方々が交流できる豊かな場に自分の身を投じたいと思っています。私の夢は、アートミーツケア学会に親子で参加することです。小学生でも参加できる学会、保育園児でも参加できる学会、おじいちゃんもおばあちゃんも是非どうぞ、そんな学会になると楽しそうだなと思っています。

現代社会が大きく変動するなか、医療や福祉、教育、コミュニティなど人間の生を支え、育む場もまた大きな変化の時代を迎えています。人間が人間を求める「ケアの時代」にあって、生の質とは何か、それを高めるとはどういうことか、幸福とは何か、豊かに生きるとはどのようなことかという疑問が提示されはじめています。
芸術の分野においても「芸術は社会にとって必要か」という問いのもと、特権的なものではなく、人間にとって、社会にとって必要な芸術のあり方が問われています。
このようななか、医療におけるアートの役割、豊かに美しく老いること、コミュニティとアートの関わり、障害と創造性、自然と癒し、テクノロジーの進歩とヘルスケアの関わりなど、アートが「芸術」の意味をこえ、人間の生きる技術としてのアートの実践が各地ではじまっています。それらのケアの現場におけるアートの実践は、想像力による生きる力の回復であり、人間らしい感性を社会システムのなかに取り戻していくための、アートの新しい可能性にほかなりません。
しかし、これらの実際の行動としてのアートは、分野を横断した多様な活動であるために、実践を体系づけ、その社会的意義、理念を探究していく場がほとんどありませんでした。
そこで、人間の生命、ケアにおけるアートの役割を研究する場として、また人間を幸福にし、人間の全体性を恢復していくためのアートの力を社会にいかしていくためのネットワークとして、アートミーツケア学会を設立することにしました。
本学会は、実質的かつ実践的に、研究者、実践者の枠をこえ、研究と現場を往還し、豊かな感性から確かな知をうみだしていくことをめざします。また、人文、社会、自然科学の分野を横断し、さまざまな社会の問題に対してアートの力を提案し、しなやかな視点をもちながら一人ひとりの物語を大切にした社会システムについて考えていきます。同時に、新しい時代における健康とは何かを考え、人間の全体性の恢復、一人ひとりが生まれ持ったいのちを花開かせることのできる社会についても考えていきます。
アートは人間の生命にどのような意味をもっているのか、そして私たちの未来に対してどのような役割を果たしていくことができるのか。積極的な生のあり方、感受性をともなった知のあり方を探究することから、新しい知と新しい美の地平をひらき、人の生きやすい社会、文化を提案したいと思います。
